2017年03月25日
在宅入門編
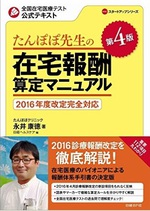
介護保険サービス給付対象まとめ
①65歳以上(第1号被保険者):自立以外の、要介護認定を受けた方(疾病の種類は関係ありません)
②40歳以上65歳未満(第2号被保険者):自立以外で、右上表の16の特定疾病に該当し、要介護認定を受けたもの
③40歳未満:介護保険サービス給付の対象外
2017年03月24日
在宅入門編
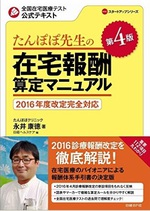
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
被保険者は、65歳以上の第1号被保険者
40歳以上65歳未満の第2号被保険者からなります。
介護保険サービスを受けられるのは、第1号被保険者と40歳以上65歳未満で脳血管疾患等の前頁の
16種類の特定疾病を有する第2号被保険者で、要介護認定を受けている事が要件となります。
※介護保険サービスを受けられなくても、ご本人の障害や疾病の内容等に応じて、障害者総合支援制度や医療保険のサービスの利用が可能です。
2017年03月23日
在宅入門編
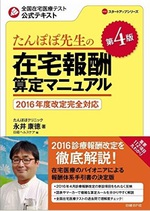
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
末期癌
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、シャイ・ドレガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎を含む)
両足の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
次回特定疾病の規定について・・・
2017年03月22日
在宅入門編
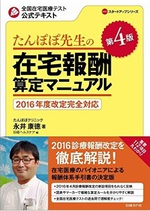
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病
介護保険サービスの給付対象
在宅医療の制度を理解するには、介護保険サービスの給付対象になるのはどのような場合かをしっかり把握しておくことが
大切です。
訪問看護や訪問リハビリテーションなど、介護保険と医療保険、障害者総合支援制度に同じサービスがある場合、
介護保険制度が優先されます
介護保険サービの給付対象を確実に把握した上で、医療保険や障害者総合支援制度の対象を理解していく必要がある。
介護保険制度は、市町村を保険者とし、40歳以上の人すべてを保険者として保険料を徴収する保険制度です。
2016年07月16日
介護保険制度の仕組み区分支給限度基準

公的介護保険制度
公的介護保険制度は、40歳以上の人を被保険者として保険料を納め、審査で要支援、要介護と認定された人に対し介護サービスを給付する制度。そこから介護費用の9割を支出して、介護サービス利用者は費用の1割を負担する。なお、2015年8月から一定以上所有者の負担割合が2割に引き上げられた。被保険者は、65歳以上の1号被保険者と、40歳以上の65歳未満の2号被保険者に分かれており、介護保険サービスの給付対象となるのは、要介護認定を受けた第1号被保険者と、要介護認定を受けた「特定疾病」を有する第2号被保険者。
介護予防の訪問・通所介護は介護保険制度改正に伴い、2018年3月までに市町村運営の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行する予定です。
高額介護サービス費支給制度
該当月の介護サービス利用者の自己負担分合計額が一定額を超えた際に自治体に申請すれば払い戻される制度。同世帯に複数の利用者がいれば払いも出される制度。


