2016年11月30日
訪問看護

訪問看護ステーションの訪問看護療養費には訪問看護基本療養費と訪問看護管理療養費がある。
訪問看護基本療養費ⅲは、退院後に訪問看護受けようとする入院患者が在宅療養に備えて一時的に外泊し、その間に訪問看護ステーションの看護師等による訪問看護を受けた場合に算定する。
訪問看護管理療養費は、主治医との連携、利用者家族への連絡相談安全管理体制の整備、休日も含め計画的な管理等の要件を満たすと算定できる。
2016年改定では、訪問看護計画書などを電子的な方法で主治医に提出する事が認められた。ただし、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」2013年10月を遵守する必要がある。
2016年11月29日
第7回全国在宅医療テスト
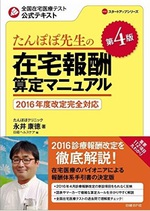
解説
問題29 小児特有の問題について正しいものを3つ選びなさい。
〇(1)この女児では、成人となっても体重が20kg未満であれば、在宅療養後方支援病院と、連携している医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理を行った場合、それぞれの医療機関において在宅療養指導管理料を算定できる。
( 15 歳未満から引き続き人工呼吸器を装着している患者であれば、体重20Kg未満の患者に限り可能)
〇(2)この女児では、在宅成分栄養経管栄養法の要件を満たす栄養剤を使用していなくても、在宅小児経管栄養法指導管理料を算定できる。
( 15 歳未満のため)
×(3)2016 年度改定で機能強化型訪問看護ステーションの要件に小児の実績が盛り込まれたが、「15 才未満の超・準超重症児の利用者数が
⇒機能強化型訪問看護管理療養費1では6人以上で、機能強化型訪問看護管理療養費2では5人以上
〇(4)この女児の場合、超重症児・準超重症児判定スコアが少なくとも25点以上になるので、超重症児となり、長時間の訪問看護が必要な場合は、週3回まで長時間訪問看護加算が算定できる。
×(5)この女児では、複数名での訪問の必要性がある場合、複数名訪問看護加算が算定できるが、看護職員と看護補助者が同行した場合は、
⇒回数制限がない。
(「厚生労働大臣が定める疾病等」「状態等」、特別訪問看護指示の場合は看護職員と看護補助者が同行した場合には回数の制限はない)
2016年11月28日
第7回全国在宅医療テスト
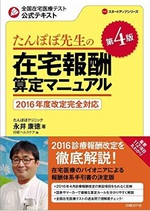
臨床問題3小児患者特有の問題について
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
問題29 小児特有の問題について正しいものを3つ選びなさい。
(1)この女児では、成人となっても体重が20kg未満であれば、在宅療養後方支援病院と、連携している医療機関がそれぞれ異なる在宅療養指導管理を行った場合、それぞれの医療機関において在宅療養指導管理料を算定できる。
(2)この女児では、在宅成分栄養経管栄養法の要件を満たす栄養剤を使用していなくても、在宅小児経管栄養法指導管理料を算定できる。
(3)2016 年度改定で機能強化型訪問看護ステーションの要件に小児の実績が盛り込まれたが、「15 才未満の超・準超重症児の利用者数が7人以上」が求められている。
(4)この女児の場合、超重症児・準超重症児判定スコアが少なくとも25点以上になるので、超重症児となり、長時間の訪問看護が必要な場合は、週3回まで長時間訪問看護加算が算定できる。
(5)この女児では、複数名での訪問の必要性がある場合、複数名訪問看護加算が算定できるが、看護職員と看護補助者が同行した場合は、週3回まで算定できる。
2016年11月27日
第7回全国在宅医療テスト
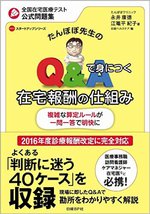
解説
問題28 訪問看護について正しいものを3つ選びなさい。
〇(1)D訪問看護ステーションとC診療所が緊急にカンファレンスを行っても在宅患者緊急時等カンファレンス加算は算定できない。
〇(2)この女児には、重症度等の高いものの特別管理加算の算定ができる。(気管切開や留置カテーテル)
×(3)このケースでは、D訪問看護ステーションが訪問看護を行った後、同日に緊急で訪問看護を行う必要がある場合、新たな別の訪問看護ステーションが緊急訪問看護加算を
⇒算定できない。
(緊急の訪問看護を算定できるのは1か月以内に訪問看護基本療養費を算定していることが要件であり新たな訪問看護ステーションではこの実績がないためできない)
×(4)24 時間の体制を整えているD訪問看護ステーションは、同意を得れば緊急時訪問看護加算を
⇒算定できない。(緊急時訪問看護加算は介護保険の加算でありこのケースでは24時間対応体制加算を算定する)
〇(5)この女児にD訪問看護ステーションは毎日の訪問看護が行えない。
( すでに訪問看護が週5回、訪問リハビリが週2回入っており、これらは同日の算定が行えないことから別の日に訪問しているため毎日どちらかが訪問していることになる。訪問リハビリの入っている日には、特別の関係のため訪問看護は入れないので不可)
2016年11月26日
第7回全国在宅医療テスト
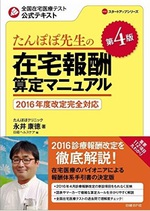
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
問題28 訪問看護について正しいものを3つ選びなさい。
(1)D訪問看護ステーションとC診療所が緊急にカンファレンスを行っても在宅患者緊急時等カンファレンス加算は算定できない。
(2)この女児には、重症度等の高いものの特別管理加算の算定ができる。
(3)このケースでは、D訪問看護ステーションが訪問看護を行った後、同日に緊急で訪問看護を行う必要がある場合、新たな別の訪問看護ステーションが緊急訪問看護加算を算定できる。
(4)24 時間の体制を整えているD訪問看護ステーションは、同意を得れば緊急時訪問看護加算を算定できる。
(5)この女児にはD 訪問看護ステーションは毎日の訪問看護が行えない。
2016年11月25日
第7回全国在宅医療テスト
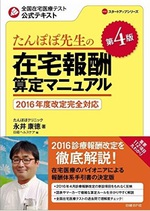
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
問題27このケースについて正しいものを3つ選びなさい。解説
×(1)この女児は療養費制度を使ったマッサージは
⇒受けられる。(筋麻痺があり受けられる)
〇(2)この女児は厚生労働大臣が定める疾病等(別表 7)にも厚生労働大臣が定める状態等(別表 8)(別表 8-2)(別表 3-1-2)のいずれにも該当する。
〇(3)主治医が特別支援学校に介護職員等喀痰吸引等指示書を発行した場合の有効期限は6か月である。
×(4)在宅患者訪問診療料の加算には、乳幼児加算はあるが
⇒乳幼児加算も、幼児加算もある(3 歳以上 6 歳未満には幼児加算もある)
〇(5)この女児には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1カ月に4回を限度に算定できる。
2016年11月24日
第7回全国在宅医療テスト
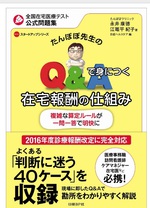
臨床問題3小児患者特有の問題について
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
問題27このケースについて正しいものを3つ選びなさい。
(1)この女児は療養費制度を使ったマッサージは受けられない。
(2)この女児は厚生労働大臣が定める疾病等(別表 7)にも厚生労働大臣が定める状態等(別表 8)(別表 8-2)(別表 3-1-2)のいずれにも該当する。
(3)主治医が特別支援学校に介護職員等喀痰吸引等指示書を発行した場合の有効期限は6か月である。
(4)在宅患者訪問診療料の加算には、乳幼児加算はあるが幼児加算はない。
(5)この女児には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1カ月に4回を限度に算定できる。
2016年11月23日
第7回全国在宅医療テスト
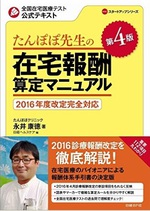
解説
臨床問題3小児患者特有の問題について
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
〇(1)この女児には訪問リハビリは週6単位までしか入ることはできない。
( 医療機関の医療保険の訪問リハビリでは、例外となるケースは末期癌、退院後、急性増悪時であり、この女児は原則の週6単位となる)
×(2)このケースでは訪問リハビリの指示は診療情報提供書を
⇒発行しない(同一医療機関が主治医のためカルテ記載でよい)
〇(3)D訪問看護ステーションの訪問看護とC診療所の訪問リハビリは、同日の算定ができない。
( 特別の関係であることから不可)
×(4)この女児に訪問リハビリで複数名の訪問を行った場合、複数名訪問看護加算が
⇒算定できない(医療機関にはこの加算はない)
〇(5) 母親に対して療養上の指導を行った場合でも、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できる。
2016年11月22日
第7回全国在宅医療テスト
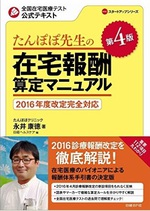
臨床問題3小児患者特有の問題について
11才頚髄損傷女児。筋麻痺があり寝たきり状態で人工呼吸器管理、気管切開、在宅酸素療法を行っている。栄養は経鼻チューブ栄養で尿バルーン留置している。主治医はC診療所の医師で、訪問看護はD訪問看護ステーションが週5回、C診療所から訪問リハビリが週2回入っている。日中は特別支援学校に通っているが吸引も頻回で、主介護者の母親の介護負担軽減が課題に挙がっている。D訪問看護ステーションとC診療所は特別の関係である。訪問服薬指導は薬局の薬剤師が行っている。
問題26
(1)この女児には訪問リハビリは週6単位までしか入ることはできない。
(2)このケースでは訪問リハビリの指示は診療情報提供書を発行する。
(3)D訪問看護ステーションの訪問看護とC診療所の訪問リハビリは、同日の算定ができない。
(4)この女児に訪問リハビリで複数名の訪問を行った場合、複数名訪問看護加算が算定できる。
(5) 母親に対して療養上の指導を行った場合でも、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定できる。
2016年11月21日
第7回全国在宅医療テスト
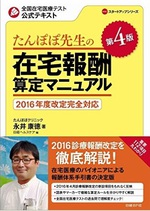
解説
問題25在宅がん医療総合診療料と看取りについて正しいものを3つ選びなさい。
〇(1)このケースで在宅がん医療総合診療料を算定する場合、保険診療上、算定できるのは、A診療所のみでB訪問看護ステーションでは、訪問看護の費用は算定できないので、A 診療所に訪問看護の費用を請求することになる。
〇(2)在宅がん医療総合診療料と在宅ターミナルケア加算、看取り加算は併算定できる。
〇(3)在宅がん医療総合診療料は、訪問診療と訪問看護の回数がそれぞれ週 1回以上であって、合計で週4日以上であることが要件だが、両方のサービスを同一日に実施した場合は1日とカウントする。
×(4)在宅がん医療総合診療料を算定していても、在宅療養指導管理料は
⇒併算定できない
×(5)在宅がん医療総合診療料を算定した場合は、緊急時の往診も
⇒算定できる。
(訪問診療を行わない日の週2回までの緊急の往診は算定できる)


