2016年08月27日
在宅患者訪問栄養食事指導料
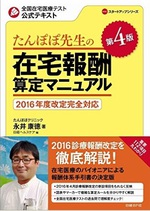
2016年度の診療報酬改定で対象患者への指導方法に関する要件が緩和されていました。
また、対象患者も拡大され、特別食の種類も増えています。
対象患者への指導方法については、改定前は「管理栄養士が患家を訪問し具体的な献立に基づきながら、実技を伴う指導を30分以上実施」しなければ同指導料は算定できませんでした。改定後は、実技を伴う指導を実施しなくても、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を行えば算定できるように改定。
対象となる患者については従来の「『厚生労働大臣が定める特別食』を必要とする在宅患者」のほか、「癌患者、摂食機能又は嚥下障害の低下した患者、低栄養状態にある患者で医師が指導の必要性を認めた者」が加えられた。在宅患者訪問栄養食事指導料において15種類が定められていた特別食には、てんかん食が追加され16種類となりました。
算定の仕組みは、従来通りで月2回まで算定可能で、同一建物居住者と同一建物居住者以外で点数が異なります。
在宅患者訪問栄養食事指導料月2回
同一建物居住者以外の場合 530点
同一建物居住者 450点
介護保険の要介護認定者については、医療保険の在宅患者訪問栄養食事指導料を算定できず、介護保険の「居宅療養管理指導費(管理栄養士が行う場合)」を算定します。【届出要】







